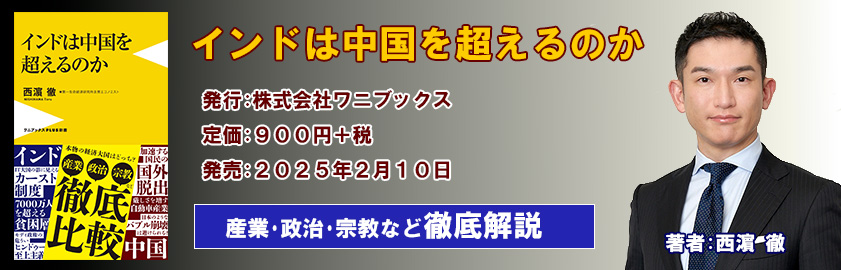- HOME
- レポート一覧
- 経済分析レポート(Trends)
- 中国・6中全会開幕、習近平指導部が採択する「歴史決議」とは
- Asia Trends
-
2021.11.08
アジア経済
米中関係
中国経済
中国・6中全会開幕、習近平指導部が採択する「歴史決議」とは
~習近平氏の権力基盤強化により政権3期目に弾みを付ける狙い、一方で人事の動きにも要注意~
西濵 徹
- 要旨
-
- 中国では本日(8日)、6中全会が開幕する。習近平指導部の2期目は残り1年となっているが、ここ数年は習近平氏への権力集中が進むとともに、任期延長を可能とする改憲実施など、事実上の終身化を見据えた取り組みも前進してきた。こうしたなか、6中全会では来秋の共産党大会への「前裁き」として注目を集めた。
- 6中全会の主要議題は「中国共産党の百年奮闘の重大な成果と歴史的経験に関する中共中央の決議」と「歴史決議」をまとめることが示された。過去に2回実施された歴史決議は、毛沢東氏及び鄧小平氏が権力基盤を強化させる契機となっており、習近平氏の3期入りに弾みを付ける狙いがうかがえる。他方、過去の歴史決議は権力闘争の色合いが強いなか、習近平氏は歴代指導者を称えるとともに、習近平指導部の実績や「共同富裕」を強力に押し出すことで表面的には党内宥和を意識した内容となる可能性が高いとみられる。
- 他方、残りの任期が1年となるなかで人事の動きにも注目が集まる。特に、党内ナンバー2の李克強氏の扱いは習近平指導部の3期目を占う上で最も注目される。これまでの動きをみれば側近重用の色合いが強まるほか、最高指導部の一段の高齢化も予想されるなど、中国をみる上でのリスク要因となる可能性もあろう。
中国では本日(8日)、6中全会(中国共産党第19期中央委員会第6回全体会議)が開幕し、11日まで4日間の日程で開催される。中国共産党の最高指導機関である中央委員会は、5年の任期中にほぼ1年ごとに1回、計7回の全体会議を開催して党の統治及び運営上の重要政策や人事といった議題を討議する。そのなかで6回目の会議においては、翌年に迫る共産党大会に向けて残りの任期が1年となるなかで党規約などに関する議題が討議されるとともに、翌年の共産党大会の開催スケジュールなどに関する決定がなされる。ちなみに、5年前の6中全会(中国共産党第18期中央委員会第6回全体会議)においては、習近平政権の2期入りを前に習近平氏を「核心」と定義するなど、歴代指導者のなかで『別格』と位置付けることのほか、習近平指導部の下で進められた『反腐敗運動』という事実上の権力闘争の強化が決定されるなど、習近平氏への権力集中が進む道筋が付けられた(注1)。中国共産党の最高指導者である総書記を巡っては、明確な任期は規定されていないものの、最高指導部である党中央政治局常務委員について『七上八下(67歳以下は留任し、68歳以上は退任)』という慣例に倣う流れが続いてきた。なお、習近平氏は今年6月に68歳を迎えており、過去の慣例に従えば来秋に予定される共産党大会(中国共産党第20回全国代表大会)において総書記職を退任することになる。しかし、2017年に開催された共産党大会(中国共産党第19回全国大会)においては、党中央政治局常務委員に次世代の起用を見送ることで『世代交代』を封じる一方、最高指導部を支える党中央政治局員に多数の側近を登用することにより習近平体制の強化を図る動きがみられた(注2)。さらに、2018年の全人代(第13期全国人民代表大会第1回全体会議)において討議、採択された憲法改正では、国家主席及び副主席の任期について連続3選禁止とした規定が撤廃されており、これによって習近平政権の3期目入りが可能となっている(注3)。このように、習近平政権の3期目入りのみならず『終身化』をも見据えた取り組みが着実に前進しているなか、来秋に予定される共産党大会において習近平氏が総書記に再任されれば、「別格の指導者による終身体制」が築かれることを意味する。習近平政権を巡っては、発足当初に掲げた「中国の夢(中華民族の偉大なる復興)」の実現にまい進するなか、2018年の憲法改正において国家の指導思想に「習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想」を加えたほか、2035年を目途とする「基本的に現代化された社会主義国」の構築、2050年を目途とする「現代化された社会主義強国」の実現を目指すなど中長期的な目標を相次いで発表してきた。今年の全人代(第13期全国人民代表大会第4回全体会議)においても2035年までの長期目標が討議されるなど(注4)、任期の延長及び終身化を前提にした政策運営を実施しており、今回の6中全会では来秋に予定される共産党大会に向けて『前裁き』となる取り組みが進むと見込まれた。
事前に発表されている今回の6中全会の主要議題は「中国共産党の百年奮闘の重大な成果と歴史的経験に関する中共中央の決議」の草案に関する審議とされており、今年は中国共産党の創建から丸100年を迎えるなかでその歴史に関する決議を行うことが示されている。いわゆる『歴史決議』は過去に2度実施されており、1回目は当時の最高指導者である毛沢東氏が中華人民共和国建国前の1945年4月に、2回目は文化大革命を経て中国が大きく混乱した後に鄧小平氏が1981年6月に行っており、今回の歴史決議は40年ぶりのものとなる。なお、毛沢東氏による歴史決議を巡っては、党内において路線対立が激化するなかで対立する党幹部を相次いで失脚させるとともに、7中全会(共産党第6期中央委員会第7回全体会議)において失脚させた幹部たちを改めて批判するとともに毛沢東氏を称える内容を盛り込んだ「若干の歴史問題に関する決議」が採択された。そして、その直後に開催された共産党大会(共産党第7期全国代表大会)においては党規約に「毛沢東思想」が盛り込まれ、その後における毛沢東氏の絶大的な権威の確立に繋がった経緯がある。他方、鄧小平氏による歴史決議は、毛沢東氏が主導した文化大革命により中国が大きく混乱したなか、1976年の毛沢東氏の死亡及び具体的な主導役となった「四人組」の失脚を受けて復権を果たした鄧小平氏により翌77年の共産党大会(共産党第11回全国代表大会)において文化大革命の終結が宣言され、1981年に開催された6中全会(共産党第11期中央委員会第6回全体会議)において文化大革命とその手段としてのプロレタリアート独裁による革命継続論を徹底的に否定するとともに、主導した毛沢東氏の誤りを指摘した「建国以来の党の若干の歴史問題に関する決議」が採択された。そして、この決議を主導した鄧小平氏は共産党中央軍事委員会主席に就任したことにより、最高指導者である党中央委員会主席ではないにも拘らず、事実上の党の最高実力者として権力基盤を固めることに繋がった。その意味では、今回の6中全会において習近平氏が主導する形で『歴史決議』を取りまとめることは、過去の歴史決議同様に自身の権威付けと自らが主導する路線の正当化を強調することにより、来秋に予定される共産党大会において異例となる『3期目入り』に弾みを付ける狙いもうかがえる。他方、過去2回の歴史決議については、上述のようにそれ以前における党内の体制及び指導者などの否定が盛り込まれてきた一方、習近平指導部の下で習近平氏個人に権力が集中する動きが強まるなか、党内においては長老などを中心に批判的な姿勢がくすぶる動きもみられる。こうしたことから、今回の決議はあくまで江沢民氏や胡錦涛氏をはじめとする歴代指導者の功績を称えつつ、習近平指導部の実績(習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想)に加え、重要なテーマとして掲げている『共同富裕』などを盛り込んだ内容になると見込まれる(注5)。
一方、来秋の共産党大会まで残りの任期が1年程度となるなか、習近平指導部が3期目入りを目指すなかではその人事の行方にも注目が集まっている。党内の序列で習近平氏に次ぐ2位にある李克強首相(国務院総理)を巡っては、現行憲法において首相任期は2期10年までとされており、2023年の全人代(第14期全国人民代表大会第1回全体会議)において退任する一方、来秋の共産党大会の時点では67歳であることから、最高指導部である共産党中央政治局常務委員に留まることで他のポストに残る可能性は考えられる。他方、習近平体制の下では習近平氏の側近が重用されるなか、習氏と李氏は折り合いが悪いとみられるなかで、次期指導部人事を巡っては慣例とされてきた定年制(七上八下)を撤廃して李氏を引退に追い込むとの見方もある。こうした背景には、習近平氏の『腹心』として政権1期目に「反腐敗運動」を主導してきた王岐山氏が2017年の共産党大会では定年制の影響で党要職を離れたものの、翌18年の全人代で国家副主席に就任して政権の『ナンバー2』になったことが影響している。なお、先月には7つの省及び自治区(河北省、黒竜江省、江蘇省、江西省、雲南省、新疆ウイグル自治区、広西チワン族自治区)においてトップ(党委員会書記)が交代しており、いずれも年齢による定年が交代理由であるなど、世代交代による党内の新陳代謝が進む動きもみられる。ただし、習近平氏の下で最高指導部は側近のみが集まるとともに、世代交代が進まず高齢化が一段と進むことも考えられるなど、中国をみていく上でのリスク要因となり得る可能性にも留意する必要があろう。
注1 2016年11月14日付レポート「ますます「全体像」が見えにくくなる中国経済」
注2 2017年10月25日付レポート「習政権2期目は「側近政治」の色合い強める」
注3 2018年3月20日付レポート「全人代閉幕、習政権は長期的野望に向けて前進」
注4 3月5日付レポート「中国2021年全人代、成長率目標(6%以上)は数値より質向上の証か」
注5 8月31日付レポート「習近平指導部が盛んに訴える「共同富裕」の向かう先とは」
西濵 徹
本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変更されることがあります。また、記載された内容は、第一生命保険ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。


- 西濵 徹
にしはま とおる
-
経済調査部 主席エコノミスト
担当: アジア、中東、アフリカ、ロシア、中南米など新興国のマクロ経済・政治分析
執筆者の最近のレポート
-
韓国中銀、政策委員は当面据え置き示唆も、新たなリスクの懸念 ~不動産高騰に加え、レバレッジ投資が株価急騰の一因に、家計債務やウォン相場にリスクは残る~
アジア経済
西濵 徹
-
タイ中銀が「背水の陣」で予想外の利下げ、構造問題に対応できるか ~バーツ高に加え、構造問題への対応で財政政策と協調も、余地が限られるなかで困難さが増すか~
アジア経済
西濵 徹
-
オーストラリアは1月もインフレ確認、RBAはタカ派傾斜を強めるか ~豪ドル高・NZドル安が続くなか、RBAのタカ派傾斜は豪ドル相場を支える展開も~
アジア経済
西濵 徹
-
中国商務部、日本の20企業・団体への軍民両用品の輸出禁止 ~中国は経済的威圧を着実に強化、日本として中国リスクの低減に向けた取り組みは不可避~
アジア経済
西濵 徹
-
米連邦最高裁が相互関税に違憲判決、新興国はどうなる? ~当面は追い風となり得るが、米国の「脅し」が通じにくくなるなか、日本としての立ち位置も重要に~
新興国経済
西濵 徹
関連テーマのレポート
-
中国商務部、日本の20企業・団体への軍民両用品の輸出禁止 ~中国は経済的威圧を着実に強化、日本として中国リスクの低減に向けた取り組みは不可避~
アジア経済
西濵 徹
-
バングラデシュ総選挙、主要野党が勝利、安定多数を確保した模様 ~選挙直前の米国との貿易協定で繊維・衣料品関連に追い風、当面は政治的安定の確保が焦点に~
アジア経済
西濵 徹
-
中国・1月物価は春節要因で鈍化も、「K字型」景気を反映している ~反内巻の効果は着実に現れるも内需は「K字型」の様相、人民元相場の動きに引き続き要注意~
アジア経済
西濵 徹
-
2026年の中国経済は「躓き」で開幕、バランスを欠く成長が続く ~2026年も比較的高い成長率目標を掲げるであろうが、抜本的な内需喚起に動く可能性は低い~
アジア経済
西濵 徹
-
アジア・パシフィック経済マンスリー:2026年1月 ~ハイテク需要を中心に輸出が増加~
アジア経済
阿原 健一郎