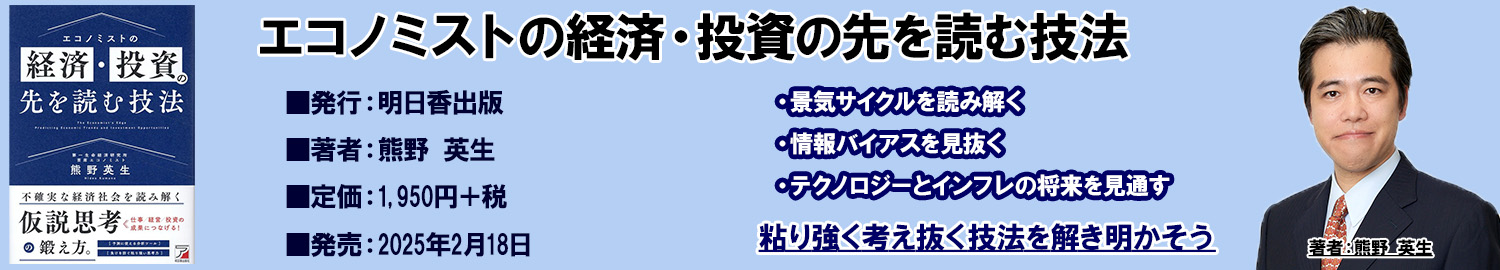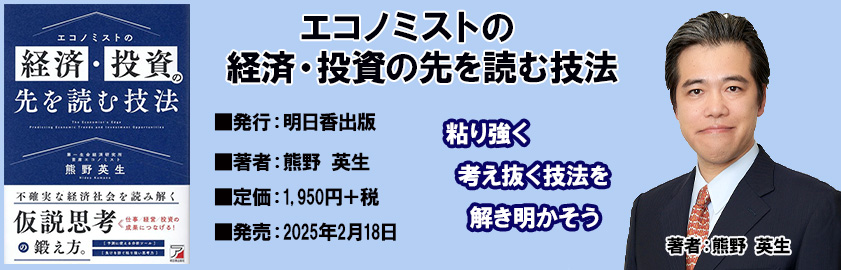- HOME
- レポート一覧
- 経済分析レポート(Trends)
- 1ドル150円に向かう円安
- 要旨
-
円安がじわじわと進んでいく。いずれ1ドル150円のラインに達するだろう。目先の為替介入の警戒感があるが、米長期金利が上昇している。そのため、今回は投機的円安とみなして断固たる措置は実行しにくい。また、介入でも円安の歯止めは一時的という可能性もある。そのときは、「次は日銀」という議論になるだろう。
再びの円安
ドル円レートは、1ドル150円にじわじわと接近しつつある(図表1)。2022年10月21日には1ドル151.94円の円安水準を付けた。日本政府は、そうした中、どこかで為替介入を強く示唆して、実際に動いてくる可能性もある。すると、円安ペースは一時足止めを食らうだろう。

しかし、達観してみれば円安傾向は止まりそうにない。米長期金利が2022年10月よりも上昇しているからだ(図表2)。そうすると、投機的円安とは必ずしも言えなくなる。介入しても、日米金利差という合理的根拠に基づく円安なのだから、介入効果は一時的なものとみなされてしまう。

岸田政権は、まずは9月中旬に内閣改造を実施して、その後で「秋」のうちに衆議院の解散という見方もある。ならば、これ以上の物価高騰で、国民の不満を助長する訳にはいかない。政府には、円安を止めたいという願望が潜在的にはある。
マーケットの方は、そうした政治的思惑とは独立したかたちで、マーケットの原理で動いている。目先の円安は一時的に足止めできても、日米金利に基づく趨勢的な円安は2023年中は止まらないと筆者は理解している。
驚きの米長期金利上昇
米長期金利が上昇することは、筆者からすれば少し意外である。常識的に考えて、長短金利が逆転すると、それは今後の景気悪化の予想が強まっていく。長短金利は時間とともにマイナス方向に広がっていくはずだ。米長期金利は低下していく。そうならないのは、米経済が予想外に強いからだ。特に、個人消費と雇用の強さである。米消費者物価は相当下がっているが、コア部分はほとんど高いままである。
米経済の先行きを語るとき、よく聞かされた言葉は、利上げの累積効果でいずれ経済減速が進むという話である。実際は、逆に、2020年以降の緩和的な金融政策、拡張的な財政政策の累積効果によって、2023年の米国経済は底堅い。2022年3月以降の利上げ効果は、それ以前の累積効果で減殺されているのだろう。
その一例は、FRBの量的引き締め(QT)が十分進んでいないことだ。FRBのバランスシートは依然として膨張したままだ。ここにはパウエル議長の再任に絡んで、FRBのテーパリングが2021年11月に遅れ、量的引き締めの開始も2022年6月になった。量的な修正のスタートが遅れたことが悔やまれる。量的には、まだ水準として緩和的なのだという解釈も成り立つ。
もう1つの論点は、中立金利が上昇していて、2022年3月以降の利上げが相対的に効きにくいという見方だ。この見方には頷ける。FRBは、四半期に一度、ロンガーラン金利というかたちで中立金利を示している。もしかすると、2023年9月のFOMCでは、従来の2.5%から上がるかもしれないという見方さえある。その場合、金融引き締めのベースライン金利が上がることになって、米長期金利も上方シフトする。すでに、それを部分的に織り込んでいる可能性もある。
9月19・20日のFOMCは注目である。政策見通しの上方修正が行われる可能性も否定できない。FRBは、7月に政策金利を+0.25%引き上げて、予告された後1回の利上げを早くも9月に実施するかもしれない。そして、2023年末までに、もう1回の利上げを示唆するサプライズも考えられる。2024年末の金利見通しで、2024年内に利下げという見方を書き換えるシナリオすらある。株式市場には大ショックになる。
日銀も頭痛の種
米国要因でドル高・円安が進むときに、日銀は何も手出しができないのか。為替介入という防衛ラインが突破されたとき、「次は日銀」という国内からの声が出るだろう。植田総裁は、7月に連続指値オペの発動ラインを1.00%に引き上げて、本当はそこでしばらく様子を見たかった。
しかし、マーケットは生き物だ。植田総裁の時間をかけるスタンスは、あまりに緩和的過ぎた。長期金利が上昇していく途中で、臨時の資金供給を行って、上昇を牽制すると、それが返って円安の引き金になった。
9~12月のどこかで政策修正をアナウンスして、今度は長期金利の上昇に寛容になるのだろうか。そうすると、7月の政策修正は、早々に手直しということになり、非常に印象が悪い。
「為替介入の次は日銀の政策修正だ」という議論が出てくると、植田総裁は困った立場になる。これは頭の痛い問題である。
熊野 英生
本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変更されることがあります。また、記載された内容は、第一生命保険ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。